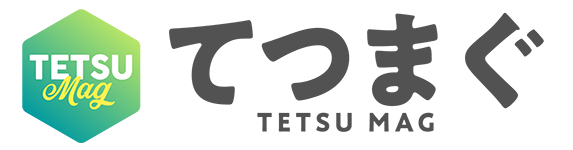横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒
一級鉄筋技能士
唎酒師
狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中
消費税が8%から10%に上げる際に、「消費税が上がれば売り上げが上がるから良い」と社長に言われたことを今でも覚えています。
当時の感覚だと意味がわからなかったのですが、今となっては「その通りだな」と思います。
「AI開発のナビゲーター資金調達編」では、補助金を利用した資金調達方法のやり方を講座化しているのですが、本当に税金というのは企業側に超有利に働いています。
日本の税金の仕組みを理解することが、今の混沌化した世の中を生き抜く必須のスキルになりつつあるのではないでしょうか。
この記事では、とっつきにくい税金、中でも一番身近な消費税について解説していこうと思います。
目次
消費税について
財務省のHPを見ると、「消費税は、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金」と記載があります。
消費税と聞いて、まずレシートが頭の中に浮かびますよね。
このように、消費税とは私たち消費者が何かしらの商品を購入する際に必ず支払う必要のある税金というイメージで、頭にこびりついています。
しかしながら、消費税法第5条には次のように記載があります。
|
1 2 |
消費税の納税義務者 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、この法律により、消費税を納める義務がある。 |
納税義務者は「事業者」なので、事業を行っていない消費者は納税義務はありません。
ここで私たちの頭の中は「?????」になります。
外国では付加価値税や売上税という名前がついている
日本の「消費税」という名前の税金は、海外では「付加価値税」や「売上税」という名前になっていることが多いです。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
VAT(Value-Added Tax / 付加価値税) ヨーロッパ諸国(イギリス、フランス、ドイツなどEU加盟国) アジアの一部(シンガポール、マレーシアなど) アフリカ、中東の多くの国々 GST(Goods and Services Tax / 商品・サービス税) オーストラリア ニュージーランド カナダ(一部州ではHSTとしても知られる) シンガポール(VATと似た仕組み) Sales Tax(売上税) アメリカ(州ごとに異なる税率で連邦レベルでは存在しない) カナダ(州によって異なる) IVA(Impuesto al Valor Agregado / 付加価値税) 中南米諸国(メキシコ、アルゼンチン、ブラジルなど) Consumption Tax(消費税) 日本(日本独自の名称) Other Names 韓国:付加価値税(부가가치세) 中国:増値税(增值税 / Zēngzhíshuì) |
このように、消費税というのは、事業者の売上に関係のある税金というのがわかりますね。
日本の「消費税」という名称はとても悪意のある名前に感じます。
実際に、消費税の納税額の計算方法は、簡易的には「売上にかかる消費税額 – 仕入れにかかる消費税額」で計算されます。
|
1 |
納付する消費税額 = 売上にかかる消費税額 - 仕入れにかかる消費税額 |
消費税とは商品の価格の10%を示しているのに過ぎない
上記で見たように、消費税は消費者には関係のない税金です。
「ん??じゃあ消費税って結局何なの?」
消費税とは、その商品そのものの価格のうちの10%に「消費税」という名前がついているのに過ぎないんですね。
税込だろうが、税別だろうが、本来消費者には関係なく、事業者の販促戦略で表記されているものです。
例えば、100円のおにぎりの場合
100円(税別)のおにぎりの方が、110円(税込み)のおにぎりよりもなんとなく買いやすい気がしませんか?
100円ショップの方が、110円ショップよりも安くて良い感じがしますよね。
実際に、財務省のHPを見てみてください。
綺麗なイラスト付きで丁寧に消費税について記載されていますが、あたかも消費者が負担する税金のように見えませんか?
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
HPより抜粋 消費税は、消費一般に対して広く公平に課される税です。 そのため、原則として全ての財貨・サービスの国内における販売、提供などが課税対象であり、事業者を納税義務者として、その売上げに対して課税されます。 また、税の累積を排除するために、事業者は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除し、その差額を納付することとされています。 ('ω')うんうんその通りだよね! 事業者に課される消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれ、最終的には消費者が負担することが予定されています。 (「直接税」と呼ばれる所得税などに対し、このように納税義務者と実質負担者が異なる税を「間接税」と呼びます。) ('ω')ん????消費者が負担することが予定??・・・・??? |
消費税の増税とは単に物価が上がっているだけ
このように、消費税とは、その商品そのものの価格の10%に「消費税」という名前がついているだけなので、消費者が納税しているわけではありません。
物価が上昇している現代では、減税を求める意見が多くの国民から出ています。
その中で、経団連の十倉会長は、「物価が上昇する中では、消費税の増税が不可欠」という趣旨の発言をしているので、多くの国民の頭の中は「??????」です。
事業者の立場であれば、当然ですよね。
なぜなら、消費税を納税しているのは事業者です。
物価(製造原価など)が上がれば、値上げをして利益を確保しようとするのは、企業としては当たり前なのですから。
物価の上昇(消費税の増税)にどう対抗すれば良い?
「消費税の増税=物価が上がっているだけ」と把握することができました。
では、この物価の上昇にどうやって対抗していけば良いのでしょうか?
大前提「事業者側」になること
物価上昇をコントロールするには、事業者側になるしか方法はありません。
消費者にものを販売する立場になれば、自身が販売する価格に物価上昇分を反映させることができます。
そのようなチャンスを死に物狂いで探し、自分で切り開いていくしかないんですね。
僕自身も後継者がいない地元事業者のM&Aの情報を毎日のように収集しています。
補助金を最大限活用しよう
多くの消費者は国が用意している制度に気づいていません。
これは本当にもったいないと思います。
昨今、世間では「103万円の壁」が話題となっています。
しかし、仮に103万円が123万円に引き上げられたとしても、年間で得られる減税効果はわずか1万円程度とされています。
政府が個人に対して予算を直接配布したり、減税を行うことは極めて稀です。
しかし、国の政策に合致した取り組みを行っている企業には、何百万円、何千万円、さらには何億円もの予算が配分されています。
「AI開発のナビゲーター資金調達編」では国が用意している補助金をどのように勝ち取れば良いのか、1時間の動画の中にノウハウを詰め込んでいます。
ぜひ活用して「消費税」を攻略してもらえたら嬉しいです。
まとめ
消費税は、商品やサービスの販売に対して課せられる税金で、消費者が支払う税金だという一般的な認識がありますが、実際には事業者が納税義務を負うものです。
日本では「消費税」という名称ですが、海外では「付加価値税」や「売上税」など、異なる名前で呼ばれています。
消費税の増税が物価上昇と結びつく中で、企業側は価格設定を柔軟に調整することで利益を確保し、事業を維持することが求められています。
消費税の増税や物価上昇に対抗するためには、消費者側でなく事業者としての立場を取ることが重要です。
物価上昇を反映した価格設定を行い、企業の利益を確保するための戦略が必要となります。
また、補助金や支援制度を活用することで、経営の安定化や成長を支える方法もあります。
これらの考え方を理解し、実践することが企業経営において非常に重要です。