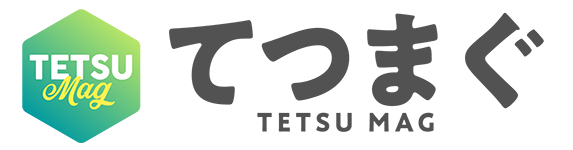横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒
一級鉄筋技能士
唎酒師
狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中
現在、日本は物価高や円安の長期化、熟練者の高齢化、人口減少に伴う事業承継問題、そして一人当たりGDPの低下といった多くの社会課題を抱えています。
こうした状況の中、国内企業が海外資本の台頭に押され、文化的価値を持つ土地や企業が外国資本によって買収されるケースも増えてきました。
これにより、日本の伝統や技術が海外へ流出してしまう懸念も指摘されています。
残念ながら資金力で勝っている外資が、日本の企業を金にものを言わせて買ってしまうんですね。
本当に悲しいことだと思います。
僕は、中国人やインド人が嫌いで、彼らに関連する二世や帰国子女も大嫌いです。(本音ですごめんなさい)
彼らは、相手の話に共感し、同調・肯定することが非常に上手で、簡単に嘘をついてくるので注意が必要です。
彼らに日本の文化を奪われるようものなら、その前に自分でその地域の文化を守りたい、と思っています。
日本の文化や技術を守るためには、国内の資本・事業者が主体的に動き、持続可能な形で事業を継承・発展させることが重要です。
この記事では、現在取り組んでいる清酒製造業の案件についてご紹介します。
目次
全国360万社の中小企業のAI普及率を上げる取り組みの中で感じたこと
近年、日本の中小企業のデジタル化が急速に進んでいると言われていますが、実態としてはまだまだ課題が山積しています。
全国に360万社以上ある中小企業の多くは、依然としてアナログな業務フローのまま運営されており、AIの活用やデータドリブンな経営には至っていません。
僕はコロナ禍以降、鉄筋工事業以外の多角化経営を目標に中小企業のAI普及率を向上させる取組を実施してきました。
特に感じたのは、日本の企業が外資との競争において超劣勢に立たされていることです。
外資が日本を買いまくっている
ニセコや白馬の例が顕著ですが、国内市場の成長が鈍化する中、外資は日本の優れた技術やブランド価値を持つ企業に注目し、積極的な買収を進めています。
特に、伝統産業やニッチな技術を持つ企業は、その独自性や価値が評価され、外資によって取り込まれるケースが増えてきました。
このような状況の背景には、資金力の差やグローバルな市場展開の巧みさがあります。
資本力のある外資は、経営が苦しくなった企業に対して魅力的な条件を提示し、買収を進めることで日本国内の産業構造に影響を及ぼしています。
札束で顔をビンタしている感じですかね。
外資が日本の補助金を使いまくっている
もう一つ見逃せないのが、日本の補助金制度の活用において、外資が巧みに制度を利用していることです。
日本政府は国内企業の成長支援のために様々な補助金を提供していますが、その多くは外資系企業にも適用されます。
その結果、海外企業が日本の補助金を活用して設備投資を行い、競争力を高める一方で、日本の中小企業は補助金の仕組みを十分に理解せずに活用できていないケースが目立ちます。
補助金の活用が進まない理由は、申請手続きの複雑さや、情報不足、専門知識を持つ人材の不足などが挙げられます。
文章が難しくて読めないんです。(僕もできれば読みたくない。)
でも外資の人間は気合とチームワークで補助金を勝ち取ってしまうんですね( ^ω^)・・・
「増税するけど、補助金あげるからもっと効率よく商売してね!」と国が制度を用意してくれているのに、それを外資が持っていくのは日本人の感覚として嫌ですが、残念ながらこれが現状です。
補助金の勝ち取り方はこちらで解説しているので、是非!youtubeでも公開してるよ!
清酒製造業の買収案件 外資から無形文化遺産を守る
色々な中小企業の話を聞く中で興味を持ったのが清酒製造業(日本酒)です。
日本酒は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されるほど、日本の伝統文化を象徴する産業の一つです。
しかし、この業界でも外資の進出が進み、日本の酒蔵が海外企業に買収されるケースが増えています。
清酒製造業免許の新規発行は行われていない
現在、日本では新たに清酒製造業免許を取得することはできません。
国税庁の規制により、新規参入が制限されており、基本的には既存の酒造業者から免許を引き継ぐしか方法がありません。
株の譲渡であれば外資でも取引ができてしまうので、なんとしてもそれだけは阻止しなければなりません。
清酒製造業免許は土地に紐づいている
面白い特徴なのが、日本の清酒製造業免許は土地と紐づいています。
例えば、「東京都渋谷区1-1-1」という土地に対して清酒製造免許が紐づいているんですね。
これは、伝統的な酒造りにおいて、その土地の水質や気候、風土が大きく影響するために設けられた制度ですが、この仕組みが外資による買収を加速させる要因にもなっています。
例えば、ある酒蔵が経営不振に陥った場合、その土地まるごと外資に買収されることで、日本の伝統的な酒造技術やブランドが海外資本の手に渡るリスクが高まります。
実際に、すでに海外資本が日本の酒蔵を買収し、海外向けに展開している事例も増えてきました。
「日本の水が外資に買収されている」と皆さんも最近耳にする機会が多いのではないでしょうか。
基本的なことができていない企業がまだまだある
清酒製造業だけではありませんが、衰退する中小企業は、経営管理の面で十分に整備されていない企業も少なくありません。
特に、以下のような課題が見受けられます。
|
1 2 3 |
管理会計の不備:正確なコスト管理や利益計算ができておらず、経営が不透明になりがち。 補助金の活用不足:前述のように、日本の中小企業は補助金制度を十分に活用できていない。 企業情報のデータ化・AI化の遅れ:業務のデジタル化が進まず、アナログな方法で運営されているため、効率化が進まない。 |
これらこそ僕が鉄筋工事企業の中で身に着けてきたスキルではないかと思いました。
これらの問題に取り組み、日本の伝統的な酒造技術を守りながら、経営の効率化を進めることで、業界の発展に貢献できればいいなと思っています。
日本酒検定2級まで取得(‘ω’)ノ
清酒の歴史を勉強するため、日本酒検定にも取り組んでいます!
ぶっちゃけ、江戸時代とか戦国時代とかの歴史には全く興味が無かったのですが、学んでみるととても面白くて1ヶ月で3級、2級を取得してしまいました。

来月の3月にはテイスティングの資格も取ろうと思っています!ではまた!